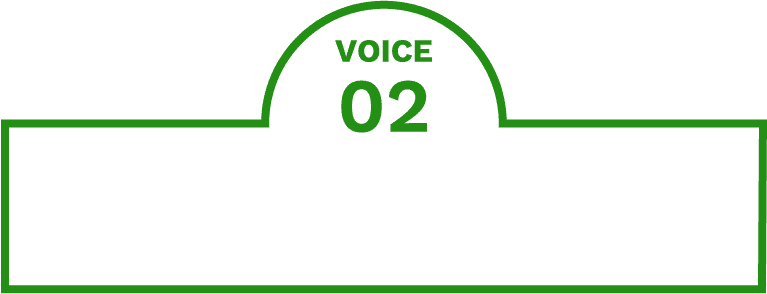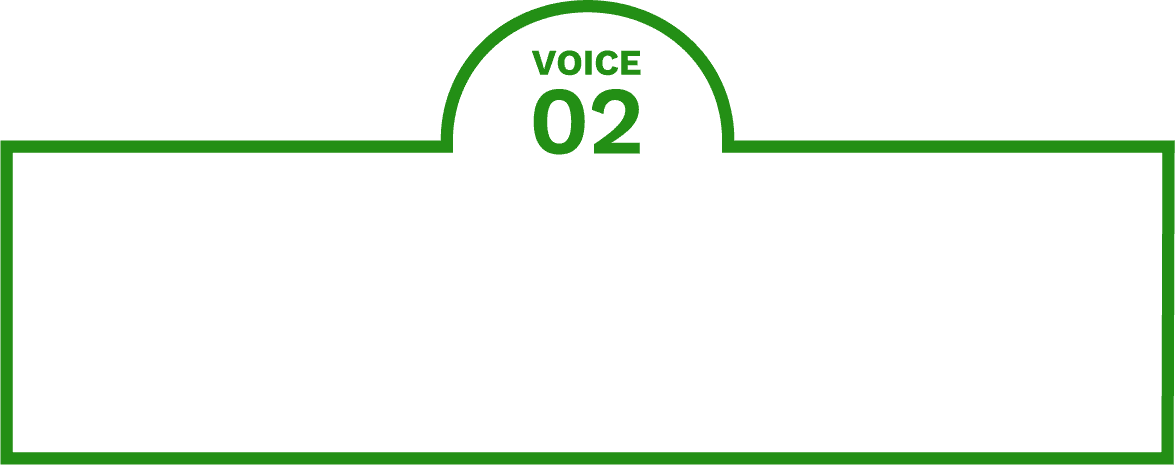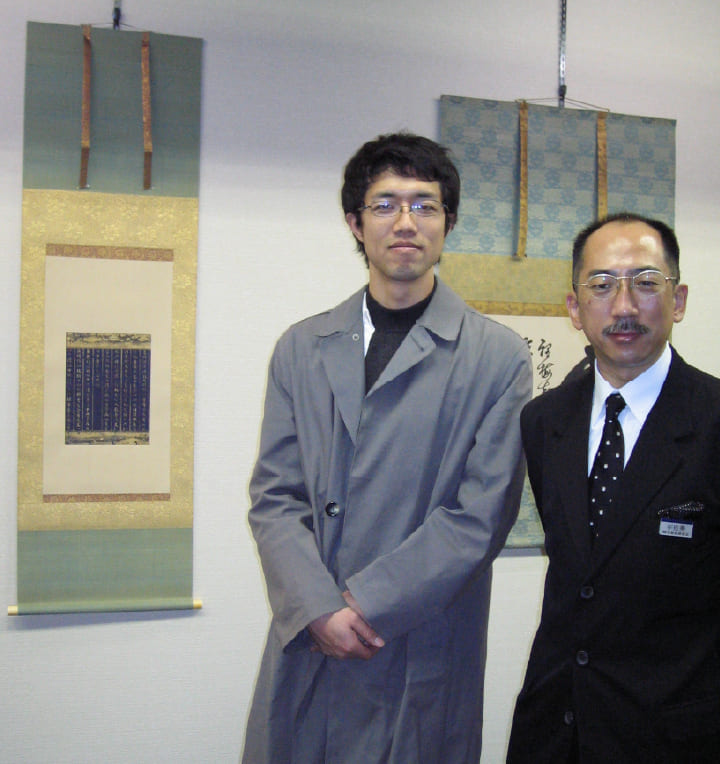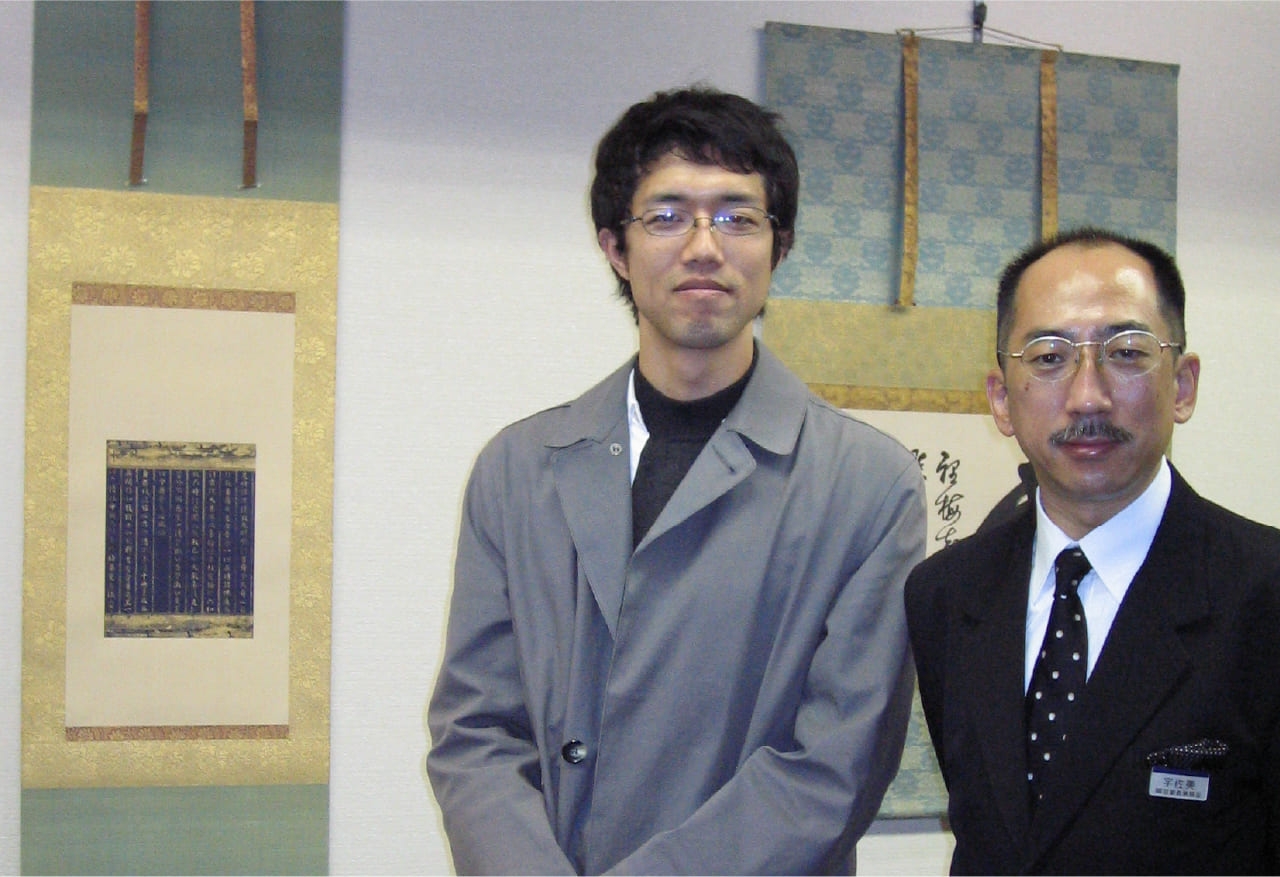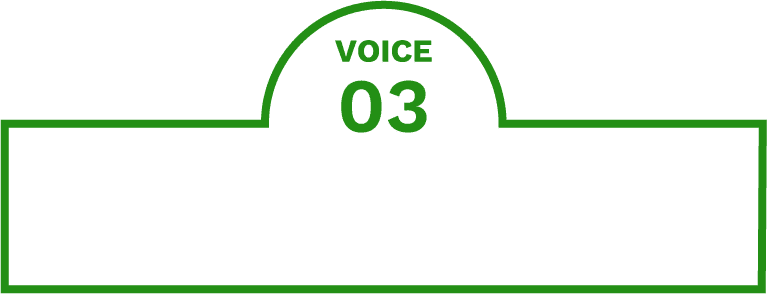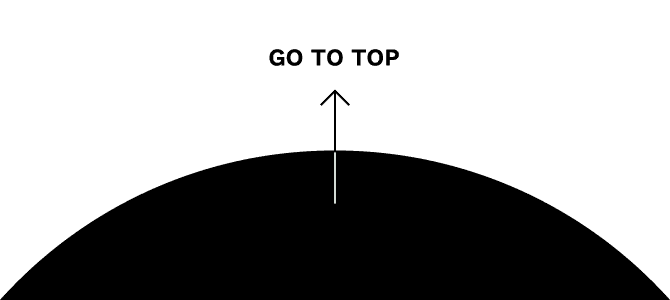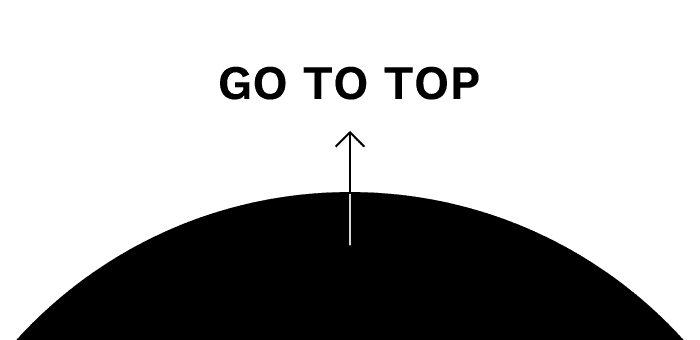(ボストン美術館 日本美術保存修復家)


1973年に英国ブライトン美術大学を卒業し、1977年に初めて日本を訪れました。最初は英語教材を扱う仕事をしていましたが、日本で暮らすうちに、美術作品の保存や修復に強い関心を持つようになりました。
西洋の修復は「科学と理論」に基づき、劣化の分析や保存環境の制御を中心に行われます。物理的な補修は最小限にとどめるのが基本です。しかし、日本の修復はまったく異なり、素材そのものに直接触れ、手を介して作品の“生命”を取り戻していく――その考え方に深く惹かれました。

東京で暮らしていた頃、京都の宇佐美松鶴堂の存在を知りました。どうしても学びたいと何度も足を運び、ようやく許可を得て、1981年から1992年まで修行させていただきました。欧米出身者として日本の伝統的な修復技術を本格的に学べたことは、かけがえのない経験です。
工房での日々は、まさに「文化を身体で学ぶ時間」でした。和紙・裂(きれ)・糊という三つの素材を単なる材料としてではなく、それぞれに“呼吸”や“気配”を感じながら扱う。糊の濃度ひとつで紙の伸びや貼りの表情が変わり、裂の選び方で作品の印象がまったく違ってくる。西洋が「構造の理解」から始まるとすれば、日本の修復は「素材との対話」から始まるのです。私はその違いに驚きながらも、職人たちの繊細な感覚を少しずつ体得していきました。


印象に残る仕事のひとつが、京都の寺院で行った障壁画や襖絵の修復です。数百年を経た作品を解体し、裏打ちを改め、修理後に再び現地で組み直すという大がかりな作業でした。湿度や温度、搬送時のわずかな変化が作品に影響を与えるため、細部まで気を配りながら慎重に進めました。そのとき実感したのが「直すのではなく、息を整える」という日本の言葉の意味です。修復とは傷を隠すことではなく、作品が再び語り始めるための呼吸を整えることなのだと学びました。
工房には職人や研究者、そして海外からの見学者も多く、伝統の中にありながら開かれた空気がありました。文化を受け継ぐとは、閉じた世界を守ることではなく、異なる文化と出会いながら本質を問い続けることなのだと感じました。異国の立場にいたからこそ、日本の修復の強みと美しさをより鮮明に理解できたのかもしれません。
十年にわたる修業の後、ライデン国立民族学博物館やボストン美術館で東洋絵画の修復に携わりました。日本で学んだ技と感覚を欧米の現場に伝えることが、自分の使命だと思っています。日本の修復には、紙の繊維の向きを指で感じ、糊の乾きを呼吸で判断するような“手の記憶”が数多くあります。私はその知を科学的な記録や映像と結びつけ、国際的な保存技術の体系に位置づけていくことを目指しています。
修復とは、作品を元の姿に戻すことではありません。作品に刻まれた時間と人の想いを、未来へ手渡す行為です。私はこれからも、日本で学んだ「息を整える」修復の心を胸に、文化の橋渡しを続けていきたいと思っています。